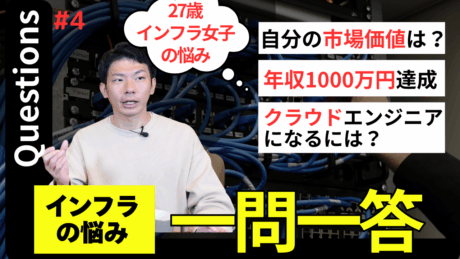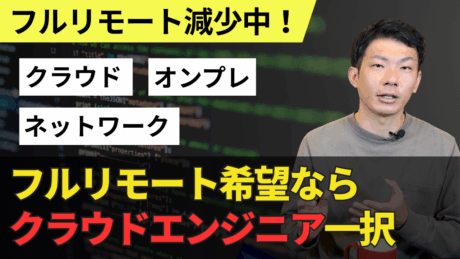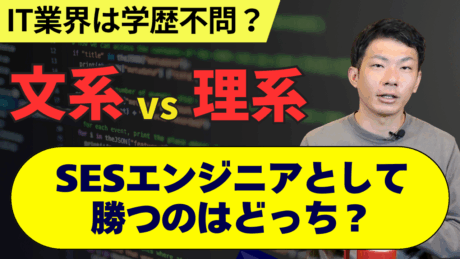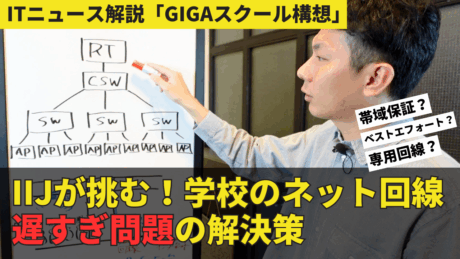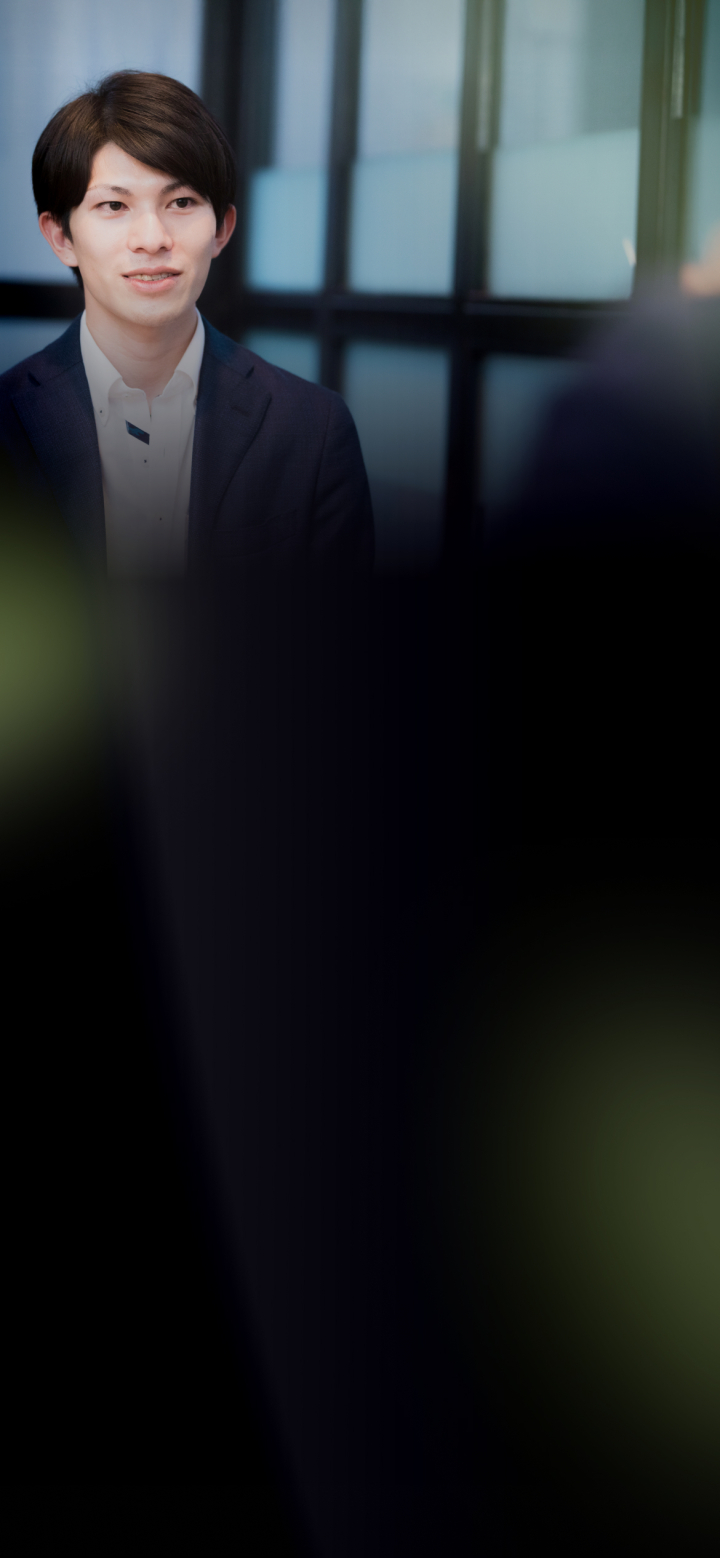インフラエンジニアにも生成AIは必要?現場で進むAI活用のリアルと今後の生き残り戦略
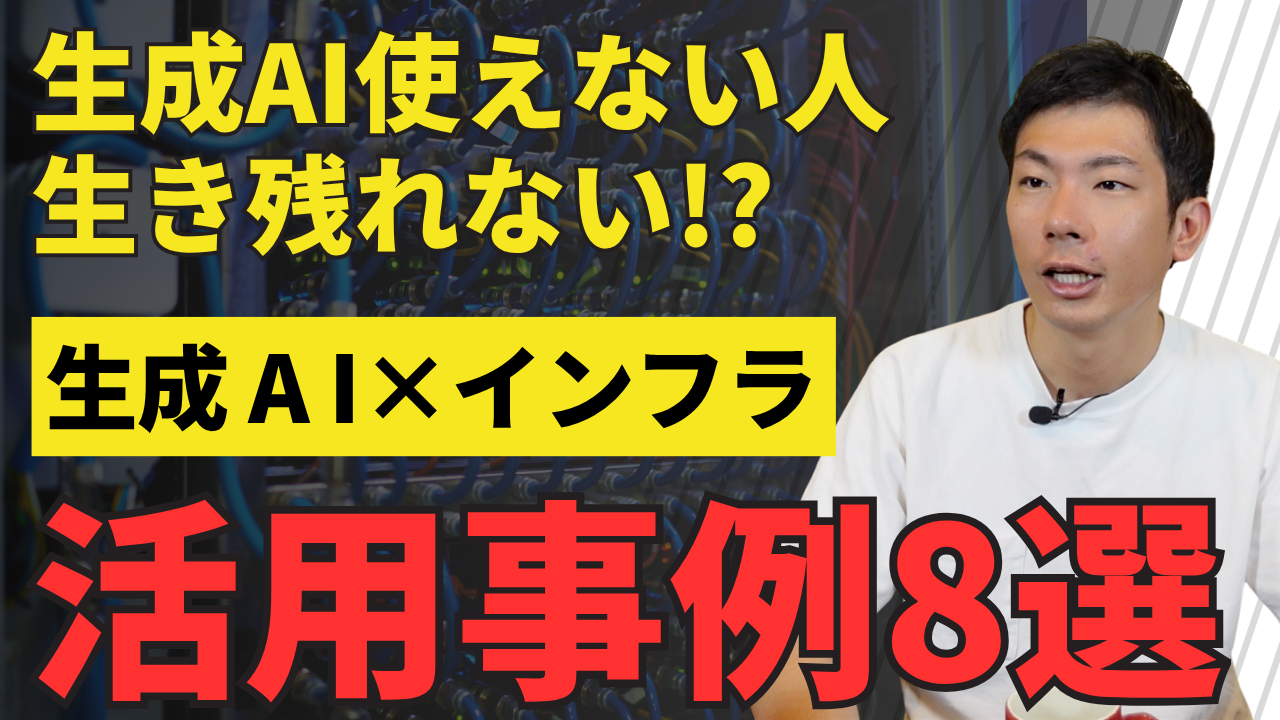
ここ数年で「生成AI(Generative AI)」の波が一気に押し寄せ、
ChatGPTやClaudeなどを日常的に活用するエンジニアも増えています。
「AIがコードを書くのは分かるけど、インフラエンジニアにも必要なの?」
そう思う方も多いかもしれません。
しかし実際には、インフラエンジニアの現場でも生成AIの活用は急速に広がっており、
使える人と使えない人の差がはっきり出始めています。
この記事では、生成AIがインフラエンジニアにとってなぜ必要不可欠になりつつあるのか、
そして実際にどのように活用されているのかを具体的に解説します。
目次
生成AIとは?検索エンジンとの決定的な違い
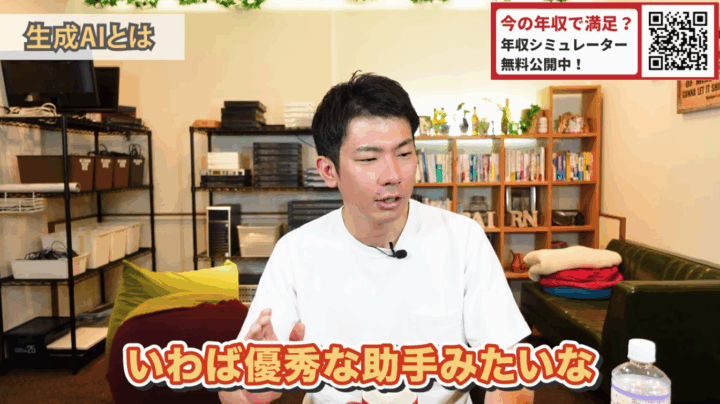
生成AIとは、人間の言葉(自然言語)で指示を出すと、文章・画像・動画・コードなどを自動で生成してくれるAIのこと。
よく「検索エンジンと何が違うの?」と聞かれますが、最大の違いは次の2点です。
-
会話ができる(質問を深掘りできる)
-
実際に作業をさせられる(コード生成・要約・翻訳など)
つまり生成AIは「情報を探す道具」ではなく、優秀なアシスタントとして使えるツールなのです。
生成AIの普及率:すでにエンジニアの4割が業務利用中
paiza株式会社の2024年11月調査によると、
現役エンジニア1349人のうち、約40%が業務で生成AIを使用。
関心・興味を持つ層も含めると、実に84.8%が生成AIに意識的に関わっているという結果が出ています。
一方で、総務省の令和6年版「情報通信白書」では、
企業レベルでの導入率は46.8%、
そのうち「積極的に活用する」と回答した企業はわずか15.7%。
つまり現時点では、個人の方が企業より先に生成AIを取り入れている状況です。
今後、企業導入が進むにつれ、AIが業務を自動化し、作業量そのものが減っていく流れは避けられません。
インフラエンジニアに生成AIが必須スキルになる理由
生成AIと聞くと「開発系のツール」という印象が強いですが、
実際にはインフラ領域と相性が抜群です。
ネットワーク設定、手順書の作成、ログ解析など、
「繰り返し・整理・検索・自動化」が多いインフラ業務は、まさに生成AIが得意とする領域。
これからは「AIに置き換えられるエンジニア」ではなく、
「AIを使いこなすエンジニア」だけが生き残る時代に入っていくでしょう。
現場でのAI活用事例8選|インフラエンジニアが実際に使っている使い方

ケルンの現役インフラエンジニアを対象に行ったアンケートから、
生成AIの実際の活用事例を8つ紹介します。
① 仕様書の要約・整理
長文の仕様書をAIに読み込ませて、
「要点だけまとめて」「構成を目次形式で整理して」などの指示を出すと、
瞬時に要約してくれます。
海外メーカーのドキュメントでも、AIに翻訳させることで理解がスムーズに。
Ctrl+F検索や英語の読解にかけていた時間を大幅に削減できます。
② 文脈ベースの検索アシスタント
「Zabbixで自動登録が失敗する原因がわからない」
といった曖昧な質問でも、AIが「ここの設定は?」「ログにこの値は出ていますか?」と
会話形式で深掘りしてくれます。
これにより、何を調べるべきかを一緒に考えてくれる検索体験が実現。
③ TeraTermマクロの自動生成
SSH操作を文章で伝えるだけで、TeraTermマクロを自動で生成。
ログ取得や一括設定などの定型処理を効率化できます。
これまで時間をかけてスクリプトを書いていたエンジニアにとって、
AIはまさに自動コーディングツールです。
④ FortiGateのVDOM検証用スクリプト生成
仮想環境でのポリシーテストを自動化するPythonコードをAIに作成させ、
検証スピードを向上。ミスの削減にもつながっています。
検証環境の構築や設定ミスの確認作業も、AIによるコード補助で効率化可能です。
⑤ IaC(Terraform/CDK)コードの叩き台生成
AWSエンジニアからは「もはやAIなしでは仕事にならない」という声も。
構成要件を伝えるだけで、TerraformやCDKのコードを生成してくれます。
さらに、エラーが出た際もそのままAIに貼り付けて「修正して」と頼むと、
自動で修正版を提示してくれるほど。
若手の手作業部分がAIに置き換わるスピードは想像以上です。
⑥ エラーメッセージの解析
エラーログを貼り付けるだけで、
原因と解決策を具体的に提示してくれるのも生成AIの強み。
「検索しても関係ないブログばかり出てくる」というストレスがなくなり、
トラブルシュートの時間を劇的に短縮できます。
⑦ コマンド・設定の確認
「証明書を作るコマンドを忘れた」
「Catalystでのインターフェース設定が思い出せない」
といったシーンでも、AIに質問すれば即答してくれます。
Cisco/Juniperなどのマルチベンダー環境では特に便利。
コマンドリファレンス代わりとしてAIを活用している人も増えています。
⑧ ナレッジベース+チャットボットの自動対応
メーカーのテクニカルサポート(TAC)部門では、
生成AIを社内ナレッジと組み合わせ、問い合わせ対応を自動化。
メール返信文までAIが生成し、一次対応をほぼ無人化しているケースもあります。
生成AIによって若手の仕事が減る未来
特に3〜5番のような自動化領域では、
これまで若手が担当していた定型業務がAIに置き換わりつつあります。
「AIが作業を奪う」のではなく、
「AIを使えないと仕事が回らない」状況に変わっていくのです。
ケルンが「生成AI」を重点技術領域に設定した理由
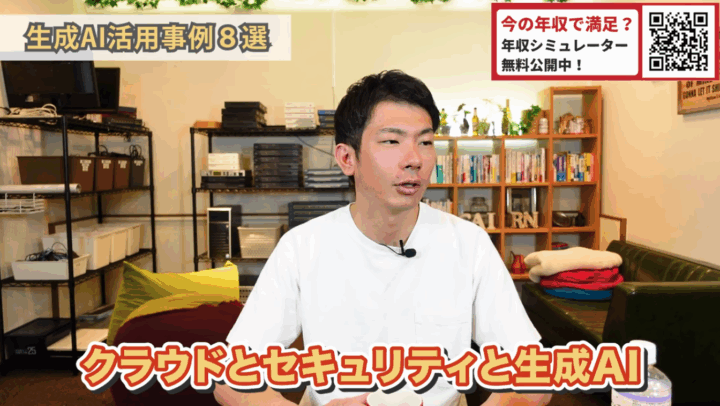
ケルンではこれまで、重点領域を
「クラウド」「セキュリティ」「無線LAN」としていましたが、
2025年から無線LANを外し新たに「生成AI」を加えました。
理由はシンプルで、
“生成AIを使いこなせるエンジニア”が、
今後インフラ業界で最も生産性の高い人材になるから。
AIを恐れるのではなく、味方にして業務を自動化する力が求められます。
まとめ|生成AIを使う側になれるかが分かれ道
-
現役エンジニアの40%がすでに業務で生成AIを活用
-
仕様書整理・コード生成・トラブル解析など、インフラ業務との親和性が高い
-
定型作業はAIに置き換わり、使えない人ほど仕事が減る
-
生成AIで学ぶではなく業務効率化のために使いこなす必要がある
生成AIはインフラエンジニアにとって、もはや特別なツールではありません。
今後は「AIを使う人」と「AIに使われる人」に分かれていくでしょう。
あなたはどちら側に立ちますか?