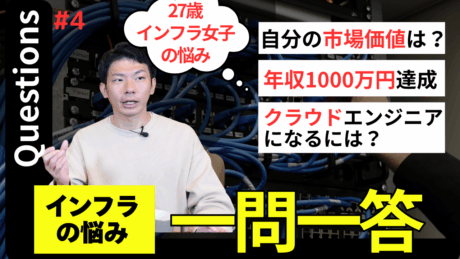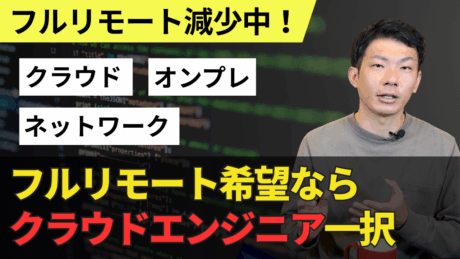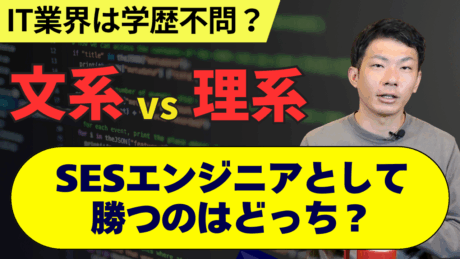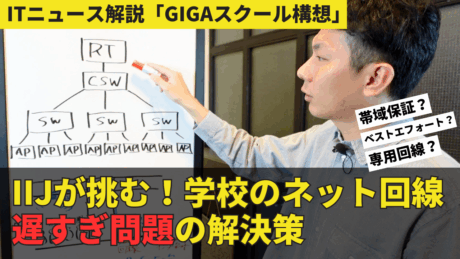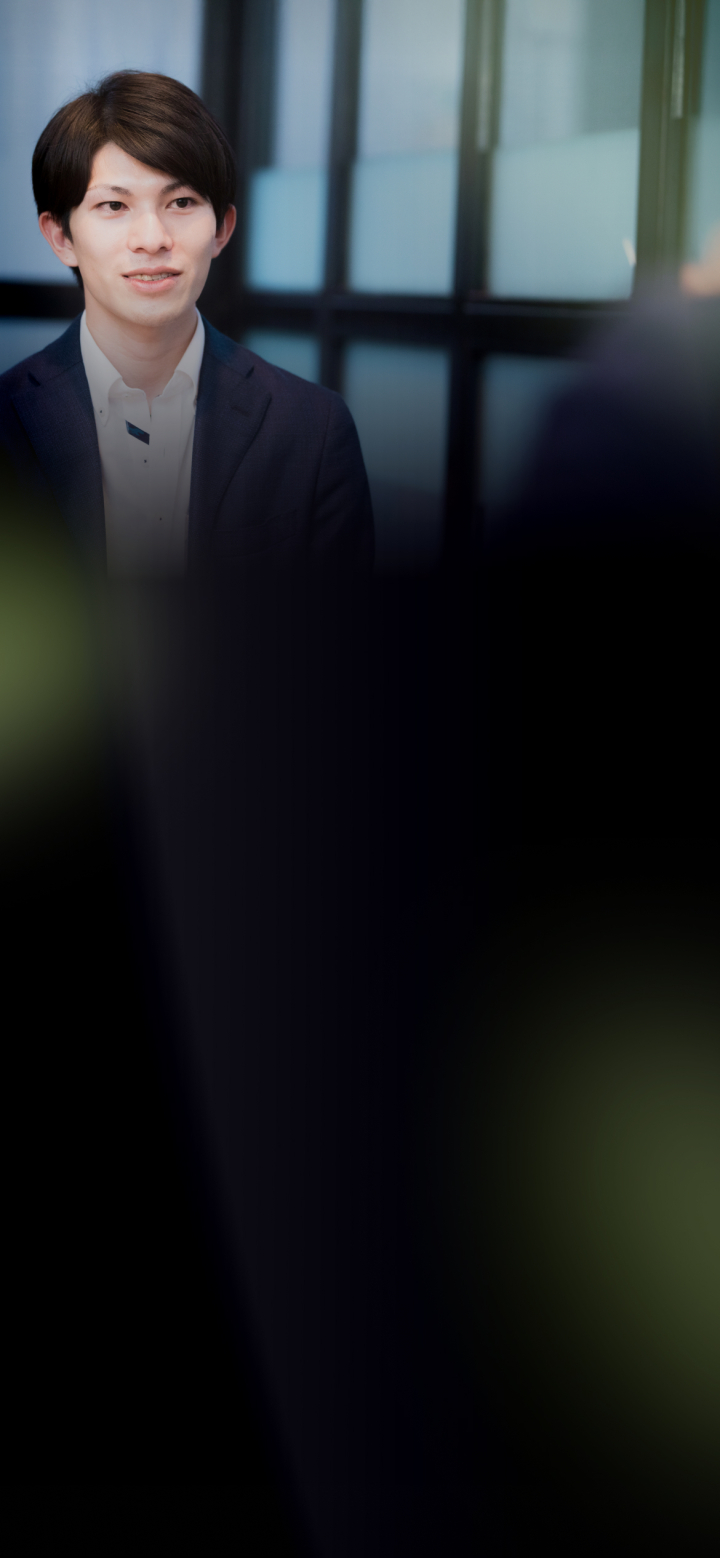チーム参画とは?高還元SESで実現が難しい理由

SES業界では、「チーム参画(体制参画)」という言葉を耳にすることがあります。
これは、エンジニアが一人ではなく複数名で同じ案件に参加する働き方を指します。
一見すると単純なように思えますが、実はこの「チーム参画」、どのSES企業でも実現できるわけではありません。
特に高還元型SESでは、社歴や営業リソースの関係で難易度が高いと言われています。
本記事では、チーム参画のメリットから実現が難しい理由、そしてインフラ特化型SES「ケルン」がどのようにしてチーム参画を成立させているのかを解説します。
目次
チーム参画とは?
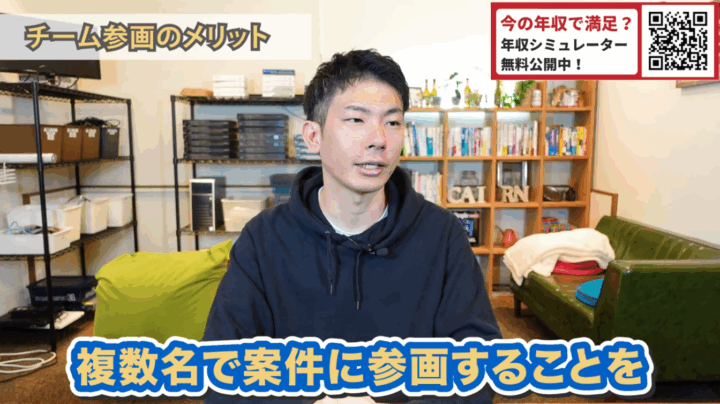
チーム参画とは、エンジニアが2名〜5名ほどのチーム単位で案件に参画する形態のこと。
個々のスキルが異なるメンバー同士が補完し合い、より高い技術力と安定した成果を提供できるのが特徴です。
例えば、ネットワーク・サーバー・クラウドといった異なる領域のメンバーが組むことで、
1人では難しい上流工程(設計・構築など)にも挑戦しやすくなります。
特に若手にとっては、同じ会社の先輩が現場にいる安心感が大きく、
質問や相談がしやすい環境が成長スピードを高めます。
チーム参画の4つのメリット
① 技術の幅が広がる
スキルの異なるメンバー同士で案件に入るため、自然と知識が共有され、技術の幅が広がります。
若手でも上流工程に挑戦しやすく、構築や設計スキルを早い段階で身につけることができます。
② 孤立しづらい
1人で常駐するSESでは、相談相手がいない孤独感や不安を抱える人も少なくありません。
しかしチーム参画なら、同じ会社の仲間と一緒に現場にいるため、気軽に相談できるという安心感があります。
③ 案件の継続率が高まる
実はチーム参画には、契約継続率を高める効果もあります。
例えば、ある現場でケルンの3人チーム(ベテラン1名+若手2名)が参画していたところ、
お客様の都合で人員削減が行われた際、他社の中堅1名ではなく、ケルンのチームが残されたという事例がありました。
理由はシンプルで、
「ベテランを残したい → 若手2名も一緒に残す必要がある」
という判断がされたためです。
このように、チーム単位で信頼関係を築けると、お客様にとっても外せないチームになれるのです。
④ マネジメント経験が積める
チームで参画することで、小規模なプロジェクトマネジメントを経験できるのも大きなメリット。
通常、個人で参画している場合は「詳細設計の一部」などタスク単位での依頼になりますが、
チーム参画では「この拠点のリプレイスをお願いします」といった塊での依頼が増えます。
これにより、
-
タスクを分解・割り振りする経験
-
お客様との打ち合わせや調整
など、リーダーとしての実務経験が積める環境になります。
チーム参画が難しい理由
では、なぜチーム参画を導入できるSES企業が少ないのでしょうか。
その理由は主に次の3点にあります。
① 商流が深くなると体制で入りづらい
発注元であるSIer(システムインテグレーター)は、本来「体制で来てほしい」と考えています。
複数の会社をバラバラに管理すると、契約処理や指示出しに手間がかかるため、1社にまとめたいのです。
しかし現実には、一次受け・二次受け・三次受け…と商流が深くなるほどチーム体制での参画は難しくなる構造にあります。
最終的には「単発1名だけの発注」になることが多く、チームを組む余地がなくなってしまいます。
② 社歴・営業力・人材層の厚さが必要
仮にチームでの発注枠を獲得できたとしても、
その枠を埋めるだけのエンジニア数とリーダー人材がいなければ受けられません。
老舗SES企業は20年以上の歴史を持ち、すでに大手SIerと太いパイプを築いています。
一方で、高還元SESの多くは2010年代後半に立ち上がった若い企業が多く、商流の浅さと営業人員の少なさがネックになりがちです。
③ インフラエンジニアの絶対数が少ない
開発エンジニアとインフラエンジニアの比率は一般的に7:3
インフラエンジニアはITエンジニアの中でも少数のため、サブカテゴリである、サーバ・ネットワーク・クラウドなどでジャンル分けすると、スキルが被る確率も低く
このため、開発とインフラが混在するSES企業では、インフラ案件でチームを組むのが構造的に難しいのです。
ケルンがチーム参画を実現できた理由

ケルンでは、この「構造的な壁」を打破するために、インフラエンジニアに特化しています。
-
社員全員がインフラエンジニア
-
ネットワーク・サーバー・クラウドの各分野で3〜4名ずつスキルが重なっている
-
毎月の案件営業数(新規・終了含む)が約10名規模
このような構造により、スキルマッチしやすくチーム体制を組みやすい環境を実現しています。
たとえばAWSリプレイス案件で5名チーム(中堅4名+若手1名)、
セキュリティ案件(SASE領域)で3名チーム(ベテラン2名+若手1名)など、
分野を問わずチーム参画の実績を積み重ねています。
高還元SESにおける新しいスタンダードへ
従来型SESは社歴が長く、チーム参画しやすい一方で、単価連動性が弱く年収が上がりにくいという課題があります。
一方、高還元SESは収入面での魅力はあるものの、社歴の短さゆえに体制参画が難しいというジレンマがありました。
ケルンはその両方を兼ね備え、
「高還元 × インフラ特化 × チーム参画」
という業界でも稀有なモデルを実現しています。
まとめ|個の努力ではなく、構造でチーム参画を実現する
チーム参画は、エンジニアにとっても企業にとってもメリットの大きい仕組みです。
しかし、それを成立させるには、営業力・人員規模・技術層の厚さが揃っていなければなりません。
ケルンでは、「努力」ではなく「構造」でそれを実現しています。
今後200名、300名と規模を拡大し、さらに大きなチーム体制で参画できるよう取り組んでいく予定です。