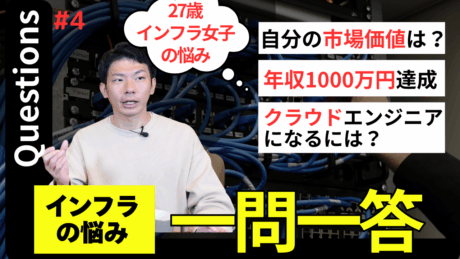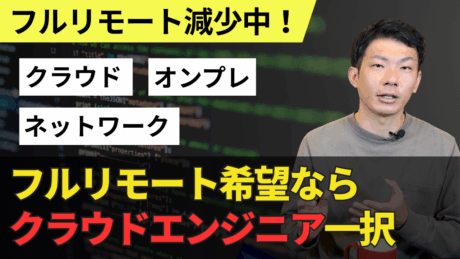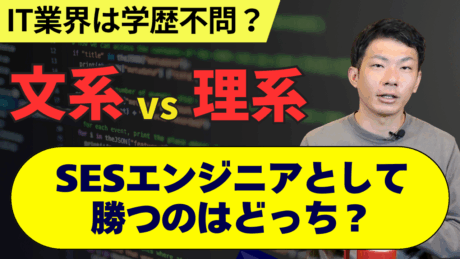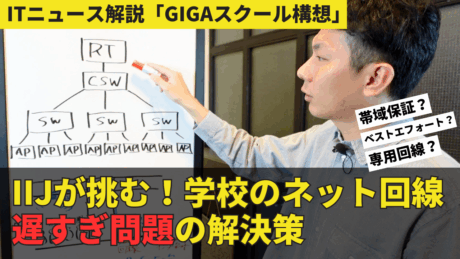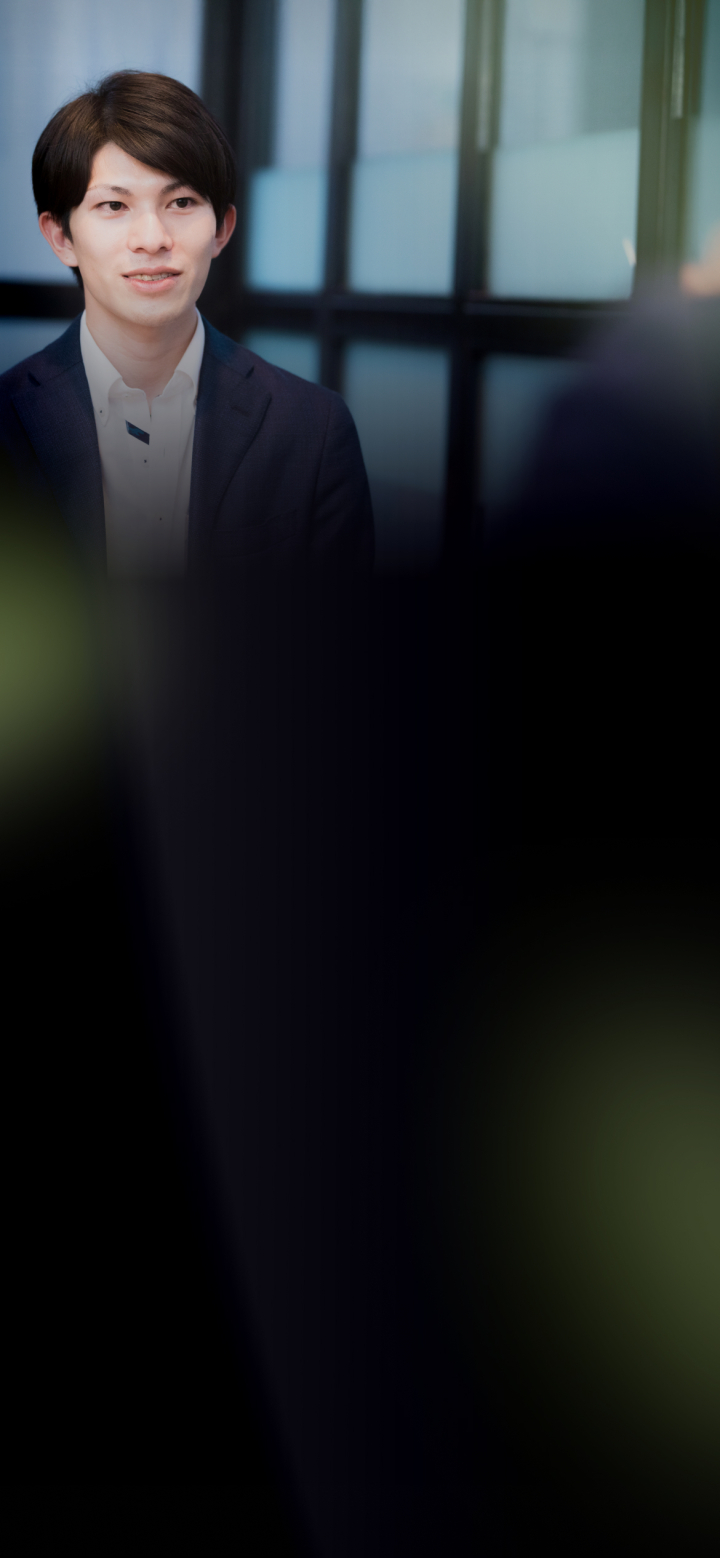インフラエンジニア やめとけ?その理由と実際の魅力を徹底解説

検索エンジンで「インフラエンジニア」と入力すると、候補に「インフラエンジニア やめとけ」という言葉が出てくることがあります。
これからIT業界を目指す人にとっては不安になるフレーズかもしれません。
確かにインフラエンジニアには「きつい」「大変」と言われる側面がありますが、同時に他の職種にはないメリットや安定感も存在します。
本記事では、インフラエンジニアがやめとけと言われる理由と、それでも選ばれる魅力について整理しました。
目次
「インフラエンジニア やめとけ」と言われる3つの理由
インフラエンジニア やめとけと言われる理由としては以下3つの理由があります。
1. 夜勤や休日出勤がある
インフラエンジニアの仕事は、サーバーやネットワーク機器といった物理的な装置を扱うため、現地で作業する必要があるケースが多いです。
-
新規設置のための現地作業
-
データセンターへの出張
-
システム停止時間に合わせた夜間・休日作業
顧客の業務に影響を与えないように、夜中や休日に作業が集中するのは珍しくありません。
これが「働き方が厳しい」と言われる大きな要因です。
2. 業務が単調に感じやすい
インフラエンジニアのキャリアは、運用監視や運用保守といった業務から始まることが多いです。
これらは手順書に従って作業することが中心で、クリックやコマンド入力を一つひとつ確認しながら進めるため、刺激が少なく単調に感じる人も少なくありません。
やる気のある人にとっては「もっと難しいことをやりたいのに」と物足りなさを感じやすく、それが「やめとけ」と言われる背景になっています。
3. リモートワークがしづらい
近年は開発系エンジニアを中心にフルリモートが増えていますが、インフラ領域は物理機器を扱うため、完全リモートは難しい傾向があります。
障害対応や現地作業がある以上、データセンターやオフィスへの出社が避けられないケースもあります。
それでもインフラエンジニアを続ける理由・魅力
では、なぜ多くのエンジニアがインフラ領域で働き続けているのでしょうか。
1. スキルアップすればリモートも可能に
運用監視や保守の段階では出社が多いですが、設計・構築など上流フェーズになると、在宅(リモート)で設計を進め、必要なときだけ現地作業に出向くスタイルが一般的です。
例えば、設計書や構成図、提案書の作成や修正業務、また、Configの作成などの資料作成は基本的にリモートでも可能な業務です。
また、クラウドエンジニアにキャリアアップすれば、開発系エンジニアに近い形でほぼフルリモートも実現できます。
2. 未経験からでも挑戦しやすい
インフラエンジニアは未経験からでも参入しやすいのが特徴です。運用監視や保守といった手順書ベースの業務が存在するため、最初のハードルは高くありません。
そこからコマンド経験を積み、構築・設計へとステップアップしていくキャリアが用意されています。
3. 技術の流行に左右されにくい安定感
開発系エンジニアは言語やフレームワークの流行に影響を受けやすいですが、インフラは基本技術が大きく変わることはありません。
-
ルーターやスイッチは役割が変わらない
-
サーバーの役割も根本は同じ
-
AIやクラウドの裏側にも必ず物理サーバーが存在する
こうした背景から、インフラエンジニアは安定した需要があり続ける職業といえます。
実際の現場エピソード
ただし、インフラエンジニアの現場は意外と“職人気質”な面もあります。
例えばネットワークエンジニアがWi-Fi機器を設置する際、建設中のビルに入り、ヘルメットや安全靴を着用して現場作業を行うこともあります。
-
工事業者と一緒に朝礼へ参加
-
設置作業後のテストで電波強度を確認
-
配線工事担当者へ配線指示を現場でサポート
空調の効かない真夏のビルで汗だくになりながら作業することもありますが、「普段入れない場所に行ける」「建物が完成していく過程を間近で見られる」など、現場ならではの面白さもあるのです。
まとめ
インフラエンジニアがやめとけと言われる理由
- 夜勤や休日作業がある
- 単調な業務からキャリアが始まる
- リモートワークがしづらい
それでも選ばれる理由
- スキルアップすればリモート環境も得られる
- 未経験でも挑戦しやすくステップアップ可能
- 技術の流行に左右されにくく需要が安定している
インフラエンジニアは決して「やめとけ」で片付けられる仕事ではありません。
大変な部分もありますが、安定性と確実な需要、そして未経験から挑戦できる間口の広さは大きな魅力です。
興味がある方は、長期的な視点でキャリアを考えながら挑戦してみてはいかがでしょうか。