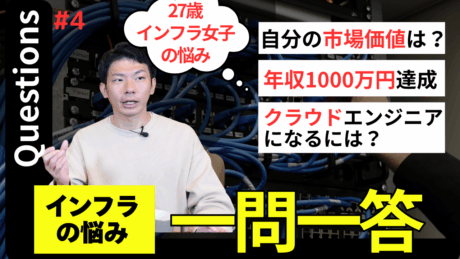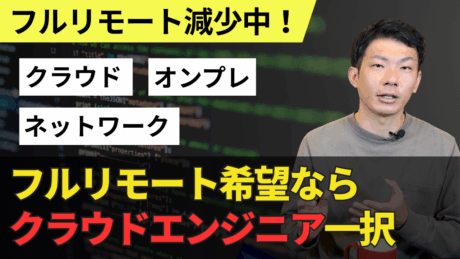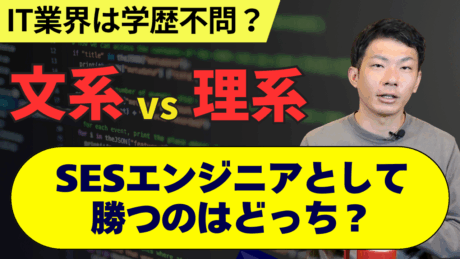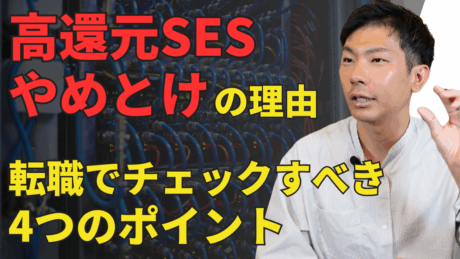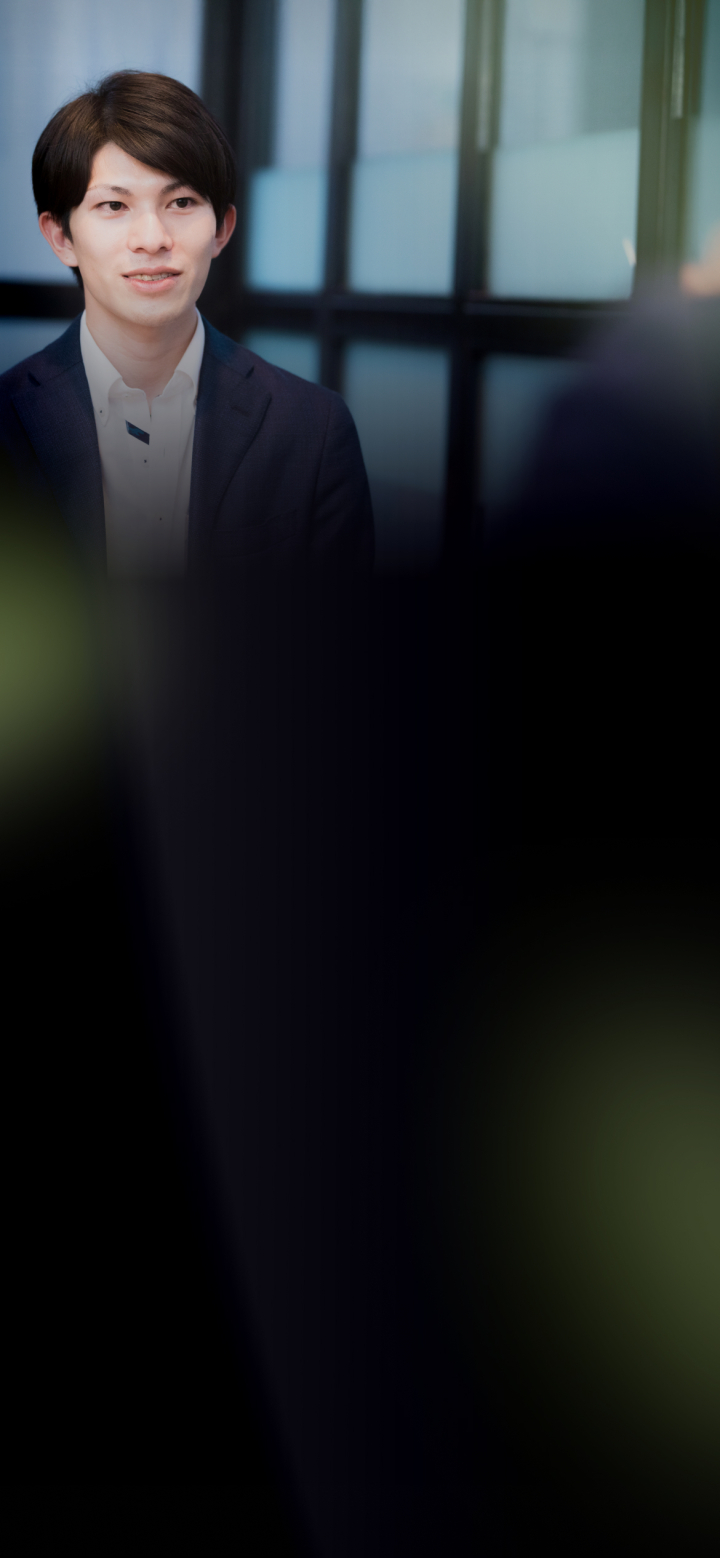投稿日:2025.10.31 最終更新日:2025.12.25
SESエンジニア退職代行の体験談。モームリを利用する背景と実態を徹底解説

近年、「退職代行を使って辞めた」という話を耳にする機会が増えました。
中でも注目されているのが、退職代行を利用するエンジニアの約7割がSES勤務だったというデータです。
これは、退職代行サービス「モームリ」を運営する株式会社アルバトロスが2023年に公表したもの。
1673人分の利用データを分析した結果、ITエンジニアのうち7割がSES企業で勤務していたことが分かりました。
この記事では、この数字の裏にあるSES業界の構造的な課題と退職代行の利用理由を、現役エンジニア・経営者の視点からわかりやすく解説します。
(参照)https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/10505/
(参照)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000103965.html
目次
なぜSES勤務のエンジニアに退職代行利用者が多いのか?

結論から言うと、「SESがブラックだから」ではなく「若手が多いから」と考えられます。
ただし、SESという働き方特有の構造も退職を後押ししているのも事実。
ここではその3つの背景を見ていきましょう。
① 若手比率が極端に高い構造
まず一つ目の要因は、SES企業に若手が集中していることです。
ある上場SES企業では、25歳以下が48%、26〜30歳が36%。
実に社員の84%が30歳未満という極端な若年層構成になっています。
SES企業の多くは「未経験から育成」を前提にしており、研修後に顧客現場で経験を積ませる仕組みを取っています。
つまり、そもそも退職率が高い“若手層”が圧倒的に多いため、結果として退職代行利用者の割合も増える構造になっているのです。
未経験で入社したものの「自分に向いていない」「思っていた仕事と違う」と感じるのは自然な流れ。
IT業界に限らず、20代での早期離職はどの業界にも見られる傾向です。
② SES特有の「帰属意識の希薄さ」
二つ目の要因は、SESという働き方特有の帰属意識の希薄さです。
SESでは、エンジニアが「自社」ではなく「お客様先」で働くのが基本。
現場の上司はクライアント企業の社員であり、自社の同僚や上司は同じ現場にいません。
そのため、相談相手がいない・評価されている実感がない・孤立しやすいといった状況に陥りがちです。
また、契約は3ヶ月更新など短期間で区切られることが多く、辞めたいと申し出ても「契約が残っているから困る」と引き止められるケースも。
「もう限界だけど、会社にも話しづらい」
「誰に相談しても分かってもらえない」
こうした状況から、退職代行を“最終手段”として選ぶ人が増えていると考えられます。
③ 「未経験歓迎」の過剰な広告が招くギャップ
三つ目の要因は、求人広告の「夢を見させすぎ」問題です。
最近では「キーボードを触ったことがなくてもOK」「年収1000万円も夢じゃない」「完全リモート」など、
未経験者を惹きつけるキャッチコピーが溢れています。
しかし実際には、SESはクライアント企業の業務を請け負うビジネスモデル。
当然ながら「未経験で技術力ゼロ」の人材に対して、いきなり高単価のIT業務を任せることはできません。
結果、企業側は「待機コスト」を避けるために、
-
コールセンター
-
IT事務
-
家電量販店での販売支援
といった非IT業務の案件にアサインするケースも出てきます。
「エンジニアになると思っていたのに、実際は販売職だった」というミスマッチが発生し、早期退職につながってしまうのです。
退職代行を利用された体験談
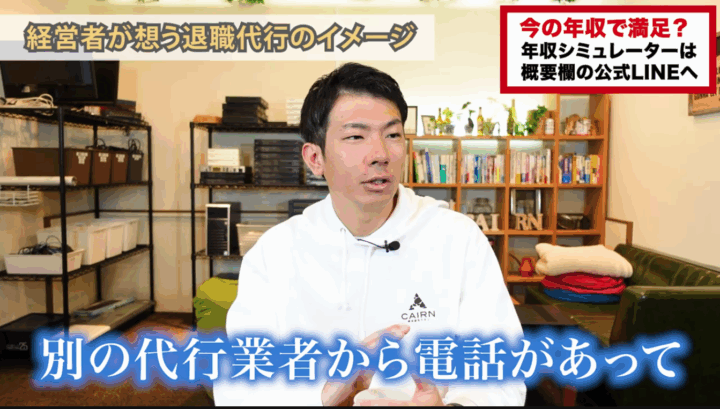
実際弊社ケルンでも、モームリではありませんが、一度だけ退職代行を利用された体験談があります。
未経験で入社したKさんは、研修を経てCCNAを取得し、設計構築案件に参画。
しかし現場の難易度が高く、入社3ヶ月で「業務が辛いので案件を変えたい」と相談がありました。
会社としては「残りの契約期間があるので、契約更新までは続けてほしい」と伝えたものの、その翌週に退職代行から連絡が入り、退職となりました。
この経験を受けて、会社では以下の改善を実施。
-
現場ヒアリング(初日・1ヶ月・3ヶ月目)を義務化
-
週次のメンタルチェック導入
-
未経験者の高難度案件アサインに制限
退職代行を使う=悪ではなく、コミュニケーション不足やミスマッチの結果として起きていることが多いと感じています。
退職代行の利用は悪ではないが、リスクもある

退職代行を使うこと自体は、自分の精神を守るという意味では決して悪いことではありません。
むしろ、弁護士や専門家が間に入ることで、法的に正しい手続きで退職できる安全な選択肢です。
ただし、同じ業界でキャリアアップを目指している方にとっては注意点もあります。
① リファレンスチェックで不利になる可能性
経験豊富なエンジニアの採用では、前職の上司へ「どんな人だったか」を確認するリファレンスチェックが行われることがあります。
その際に「退職代行で辞めた」と知られると、企業側が不安を感じるケースもあります。
② 客先のブラックリストに載るリスク
常駐していた現場で退職代行を使うと、「この人は突然辞めた」と記録が残る場合も。
その後、別の企業を通じて同じ現場に配属される際に、契約が取り消されるリスクもあります。
つまり、退職代行は最後の手段として慎重に使うべきということです。
まとめ|退職代行の「7割SES」は業界構造の問題
退職代行を使うエンジニアの7割がSES勤務というデータは、
単に「SESが悪い」のではなく、以下の3つの要因が重なった結果です。
- 若手・未経験者が多い構造的特徴
- 客先常駐による帰属意識の欠如
- 求人広告の過剰な期待演出によるミスマッチ
退職代行は決して非常識ではなく、労働者が自分を守るための合理的な手段でもあります。
ただし、将来同業界でキャリアを積みたい人は、使い方やタイミングを慎重に判断することが大切です。