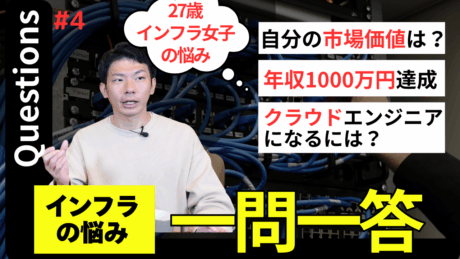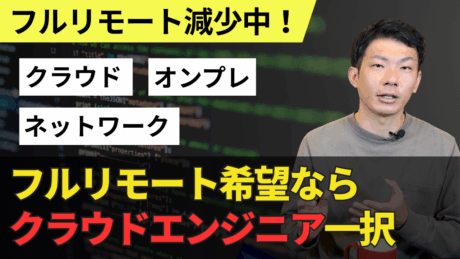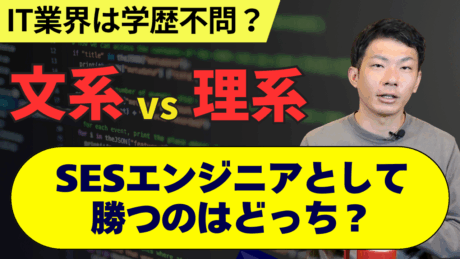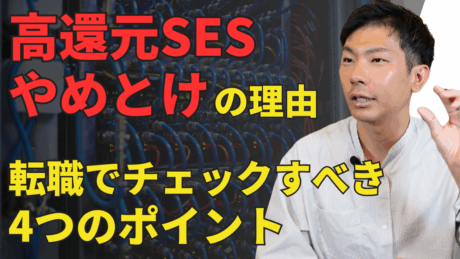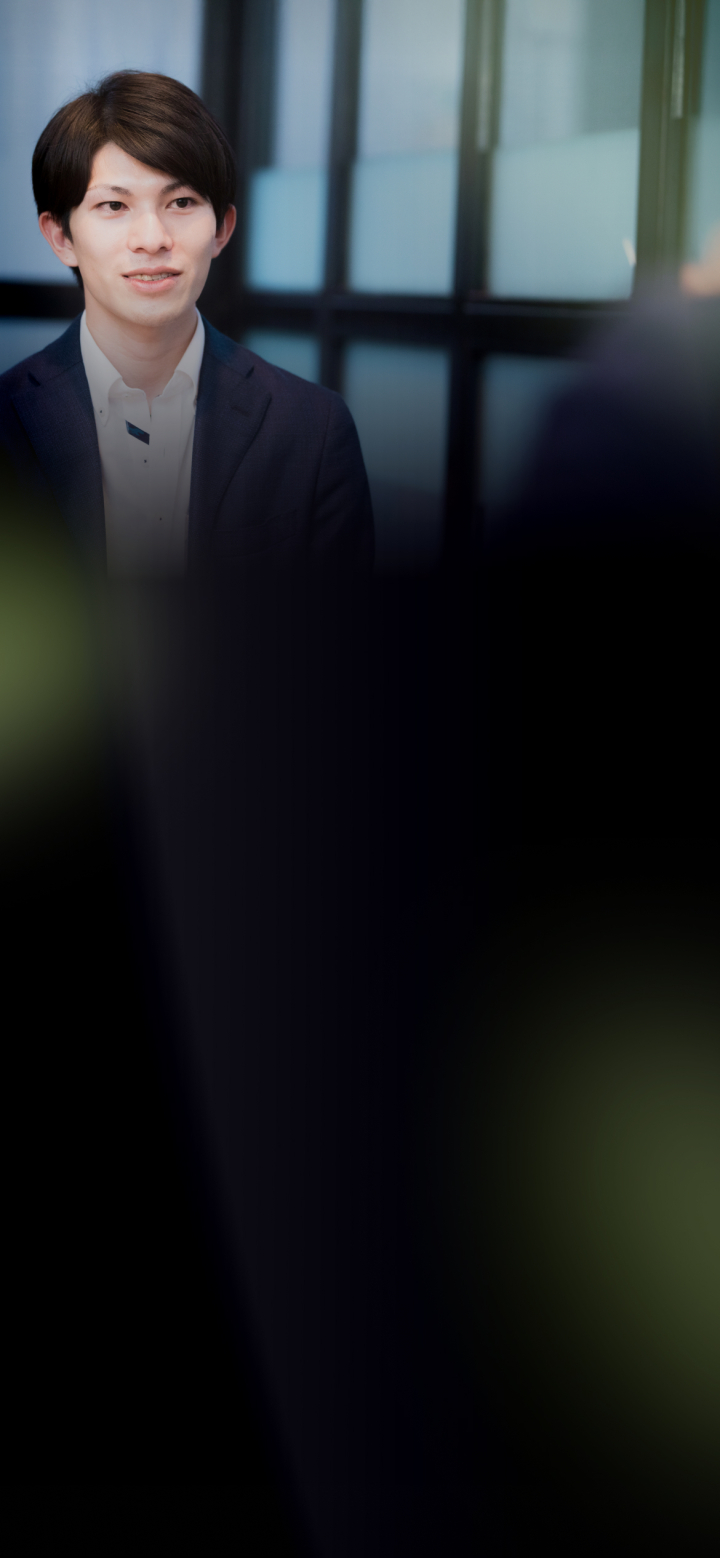投稿日:2025.09.20 最終更新日:2025.09.22
案件選択制度は諸刃の剣?メリットとデメリットを徹底解説
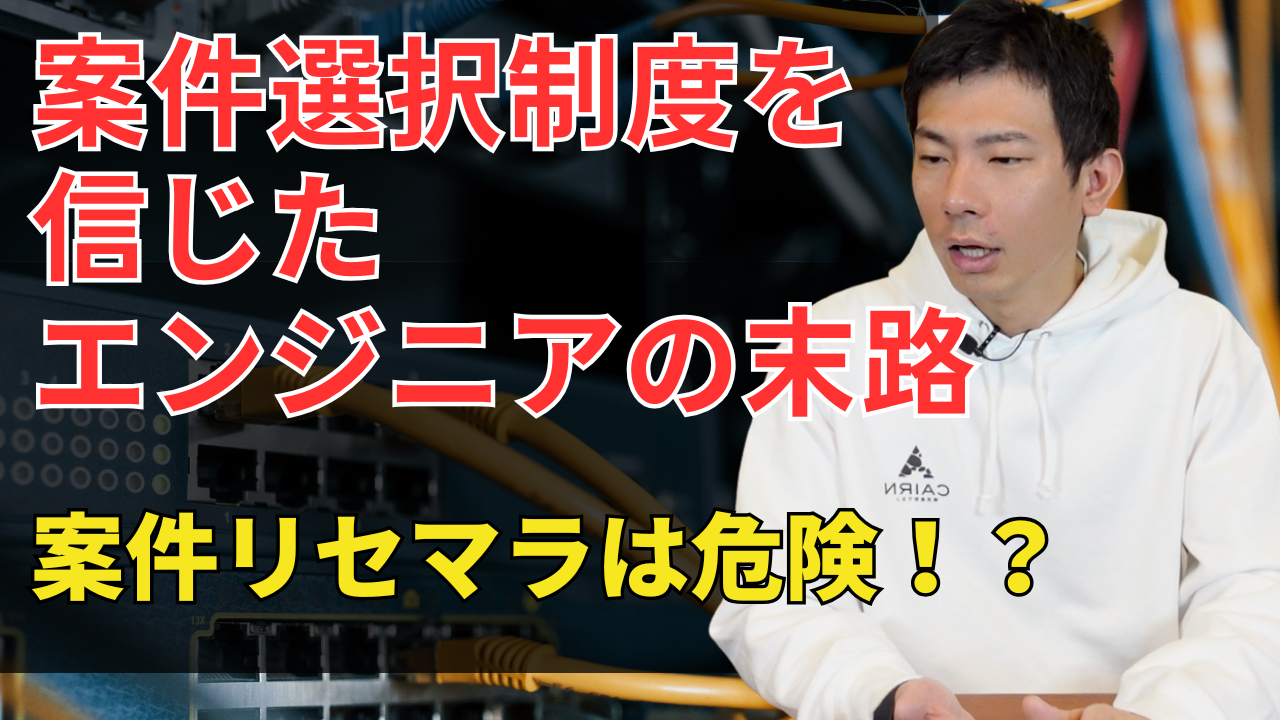
近年の高還元SES企業で広く導入されているのが「案件選択制度」です。
これはエンジニアが自ら案件を選べる仕組みで、従来のSES企業のように営業に決められるのではなく、自分のキャリアに沿った案件を選択できる点が大きな魅力とされています。
一方で、この制度にはメリットだけでなくデメリットも存在します。
特に若手のエンジニアの方は使い方を誤ると、キャリア形成に悪影響を及ぼしたり、成長の機会を逃してしまうリスクもあります。
本記事では、案件選択制度のメリットとデメリット、そして上手に活用するための考え方について解説します。
目次
案件選択制度とは?
案件選択制度とは、高還元SES企業に所属するエンジニアが参画する案件を自ら選べる仕組みです。
従来のSESでは営業が案件を決定し、エンジニアは突然面談に呼ばれ、そのまま参画するというケースが一般的でした。そのため、キャリア形成に主体性を持てず、成長の機会を逃すことも少なくありませんでした。
しかし高還元SES企業の増加により案件選択制度が普及したことで、エンジニアは自身の希望に合った案件を選べるようになり、キャリアの納得感やモチベーション向上につながっています。
案件選択制度のメリット
1. キャリア形成の納得感が高い
自分の希望に沿った案件を選べるため、キャリアの方向性に対して納得感を持って働けます。
その結果、モチベーション高く業務に取り組むことができます。
2. 案件の変更がしやすい
従来型SESでは、一度案件に入ると数年単位で同じ現場に留め置かれることも珍しくありませんでした。
営業に相談しても「後任が育つまで頑張ってほしい」と言われ、なかなか抜けられないという話もよく聞かれます。
案件選択制度では、希望すれば比較的スムーズに案件を変更できるため、キャリアの柔軟性が高まります。
案件選択制度のデメリット
この様に案件選択制度にはエンジニアが案件を選べるというメリットがある中で、実際にはデメリットも存在します。
1. 成長機会を逃しやすい
人はどうしても「自分にできること」「慣れていること」を選びがちです。
例えば構築経験がある人は構築案件を選び続け、マネジメントやリーダー業務を避ける傾向があります。
これでは成長の機会が失われ、キャリアが停滞してしまいます。
2. 市場価値が下がるリスク
詳細設計や構築スキルは数年で習得できますが、マネジメントスキルや要件定義の経験は年数をかけて積み上げる必要があります。
40代以降でマネジメント経験がないと、若手と同じ土俵で競争せざるを得ず、市場価値が下がるリスクがあります。
3. 条件重視で経験を犠牲にする可能性
「テレワーク必須」「夜勤NG」「単価は最低○万円以上」と条件を増やすほど案件の選択肢は狭まります。
結果として、肝心な技術経験やキャリアに必要な要素を積めないケースも多くなります。
この様に案件選択制度があるが故に自分のスキルの範囲でしか案件を選ばないなど、キャリア形成に影響を及ぼすことがあるのです。
案件リセマラの危険性
さらに、最近は「案件リセマラ」状態に陥っているエンジニアの経歴書を見かけることも増えています。
案件リセマラとは案件に参画した後、すぐに「ハズレ案件」と判断して離脱し、新しい案件を探す行為を指します。
一見すると柔軟に見えますが、経歴書に短期離脱が並ぶと「すぐ辞める人」という印象を持たれ、案件紹介の数が減ってしまいます。
結果的に案件を選べる自由があっても、肝心の選択肢が狭まり、炎上案件など条件の悪い現場にしか入れなくなるリスクがあります。
案件選択制度を活用するためのポイント
1. 自己規律を持つ
案件選択制度は「諸刃の剣」です。自由に選べるからこそ、あえてチャレンジングな案件を選び、経験を積む姿勢が求められます。
2. 営業との二人三脚
案件情報はエンジニアだけでは判断が難しい部分があります。営業が客観的な情報を提供し、メリット・デメリットを伝えた上で、最終的にエンジニアが選ぶ形が理想です。営業との信頼関係を築き、キャリアデザインを一緒に考えていくことが重要です。
3. 短期離脱は避ける
パワハラや過度な残業といった例外を除き、短期間で案件を転々とするのは避けましょう。多少の環境ストレスに適応する力も、社会人としての重要なスキルです。
特に、若手エンジニアは自身のスキルからどのような案件を選べば良いのかが判断できず、案件選びに失敗してしまうというパターンも多く見かけます。
そのため、エンジニアは営業と二人三脚でキャリアパスを考えることが重要です。
まとめ
-
案件選択制度は、高還元SESで普及しているエンジニア主体の仕組み。
-
メリットは「キャリア形成の納得感」と「案件変更の柔軟性」。
-
デメリットは「成長機会の喪失」「市場価値低下のリスク」「条件重視による経験不足」。
-
案件リセマラは経歴を傷つけ、逆に案件の選択肢を狭めてしまう。
-
自己規律と営業との協力を前提に、長期的なキャリアを意識した案件選びが不可欠。
案件選択制度はエンジニアにとって大きな武器である一方、使い方を誤ればキャリアを損なうリスクがあります。制度のメリットとデメリットを理解し、営業と二人三脚でキャリアを設計していくことが、エンジニアとしての成長と市場価値を高めるための鍵になるでしょう。