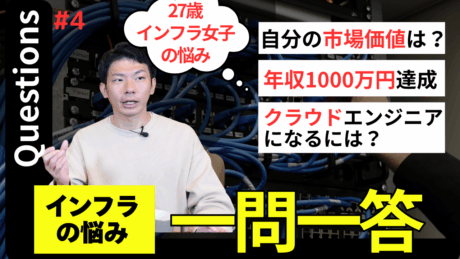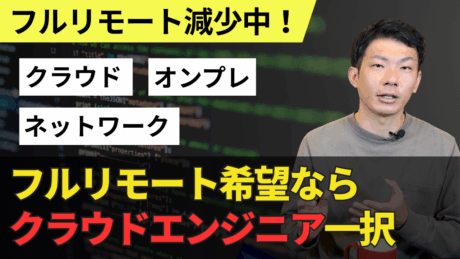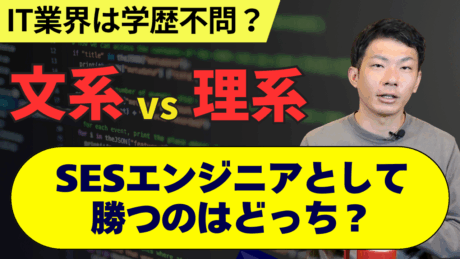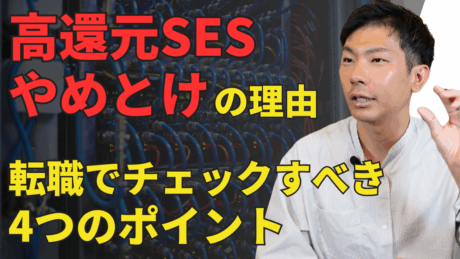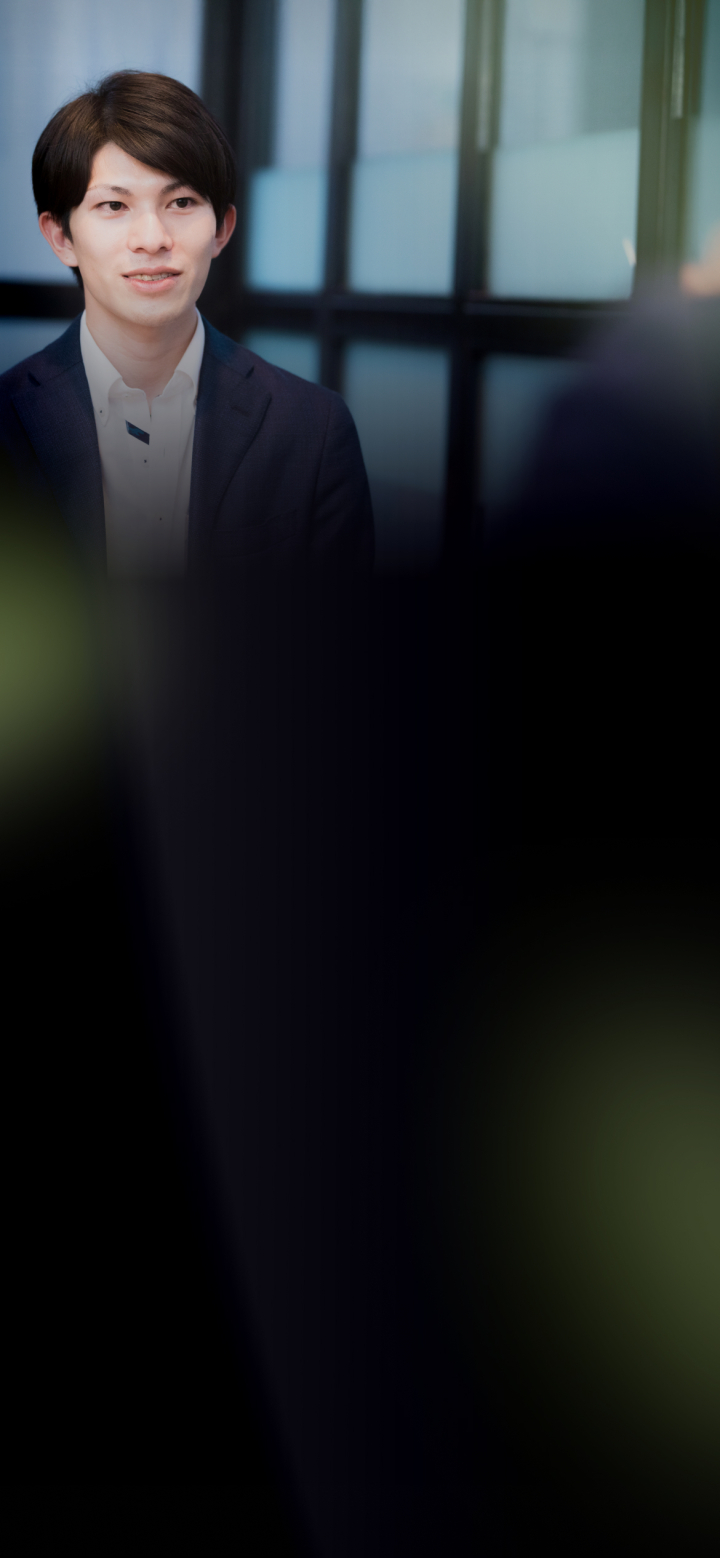投稿日:2025.09.07 最終更新日:2025.12.15
SESとSIerの違いを徹底解説|仕事内容・契約形態・キャリアパスまで比較

ITエンジニアの働き方を調べていると、
「SESはやめとけ」「SIerは激務」といったネガティブな言葉を目にすることが多く、不安になる方も多いのではないでしょうか。
しかし、SESとSIerは単純に「良い・悪い」で比較できるものではありません。
契約形態・働き方・キャリアの積み方が根本的に異なるため、自分の方向性やキャリアの段階によって最適解が変わります。
この記事では、
-
SESとは何か
-
SIerとは何か
-
SESとSIerの違い
-
それぞれのメリット・デメリット
-
どちらを選ぶべきかの判断基準
を整理し、これから転職を考えているインフラエンジニアの方へ、「SESとSIer、結局どっちがいいのか?」という疑問に答えます。
目次
SESとは?(システムエンジニアリングサービス)
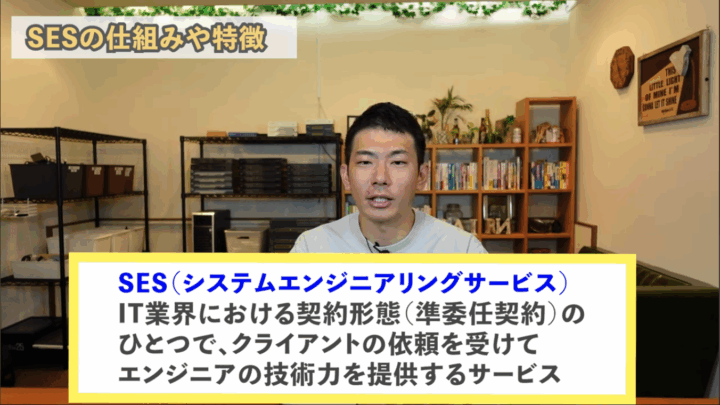
SES(System Engineering Service)とは、
エンジニアが顧客先に常駐し、技術力を提供する契約形態を指します。
SESの特徴
-
契約形態:準委任契約が中心
-
成果物の完成責任は負わない
-
一定期間、技術支援を行う
-
勤務場所は顧客企業(常駐)
派遣と混同されがちですが、
SESは「労働力の提供」ではなく「技術力の提供」である点が異なります。
業務内容は、
-
サーバー・ネットワークの運用保守
-
インフラ構築
-
アプリケーション開発支援
など、案件によって幅広く変わります。
SIerとは?(システムインテグレーター)
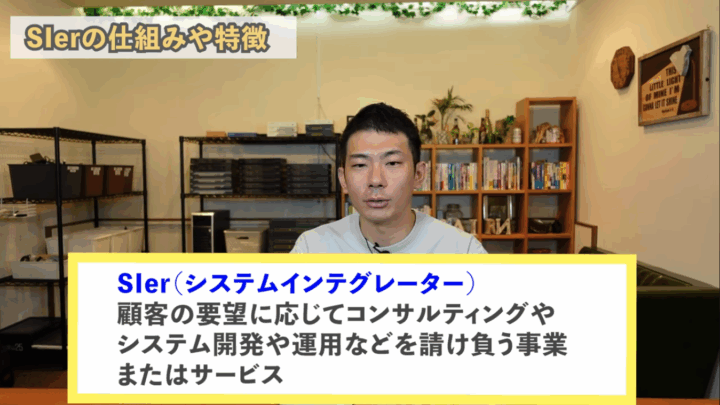
SIer(System Integrator)は、
顧客からシステム開発を請け負い、完成責任を持って納品する企業です。
SIerの特徴
-
契約形態:請負契約が中心
-
要件定義〜設計〜開発〜納品までを一括管理
-
プロジェクトマネジメントが重要
-
自社内作業が中心(常駐は少なめ)
SIerは単なる開発会社ではなく、
「システム全体を設計・統合する立場」です。
SESとSIerの決定的な違い
SESとSIerの違いを比較表で整理しました。
| 項目 | SES | SIer |
|---|---|---|
| 契約形態 | 準委任契約 | 請負契約 |
| 責任範囲 | 技術提供 | システム完成責任 |
| 勤務場所 | 顧客先常駐 | 自社 or プロジェクト拠点 |
| 業務範囲 | 設計構築現場でのメンバーポジションが中心 | 上流〜下流まで |
| キャリア | 技術特化型になりやすい | マネジメント寄り |
比較表からも分かる通り、SIerは顧客から依頼を受けた案件のシステム構築・完成・納品・検収までを行う責任があるため、業務範囲は上流から下流まで多岐にわたります。
また、SIerはSESを雇う立場にあるため必然的にマネジメントポジションになりやすいというのが実情です。
この違いを理解せずに選ぶと、
「思っていた働き方と違った」とミスマッチが起きやすくなります。
SESのメリットとデメリット
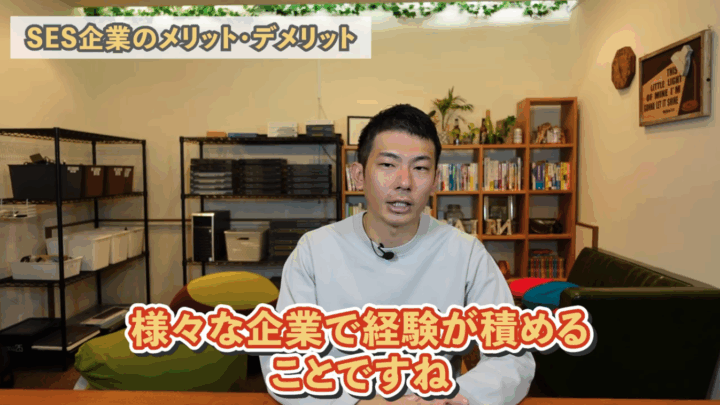
SESのメリット
幅広い現場経験を積める
SESでは案件ごとに参画先が変わるため、
業界・技術・環境の異なる現場を経験できます。
-
オンプレミス
-
クラウド(AWS / Azure)
-
運用保守から設計構築まで
技術の引き出しを増やしたい人には向いています。
キャリアの方向転換がしやすい
契約期間終了を機に、
次は「構築寄り」「クラウド案件」など、比較的柔軟に方向転換できます。
SESのデメリット
給与水準が低くなりやすい
SESは多重下請け構造になりやすく、
元請け → 二次請け → 三次請け…とマージンが引かれます。
その結果、
エンジニア本人の給与が上がりにくいという問題があります。
上流工程の経験が積みにくい
要件定義やプロジェクト管理は元請けSIerが担うことが多く、
SESエンジニアは詳細設計や構築・運用が中心になりがちです。
SIerのメリットとデメリット
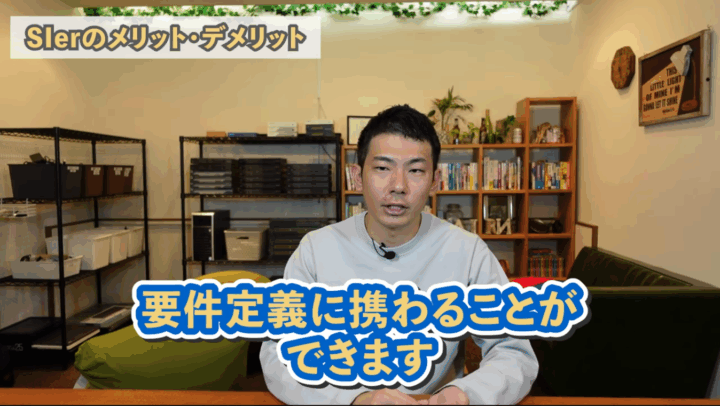
SIerのメリット
上流工程から携われる
SIerでは、要件定義・設計・進捗管理など、
プロジェクト全体を統括するマネジメント経験を積みやすいです。
これは将来的に
-
PM
-
ITコンサル
-
上流SE
を目指す上で大きな強みになります。
システム全体を理解できる
部分作業ではなく、
「なぜこの設計なのか」「どういう業務要件なのか」
を理解しながら仕事ができます。
SIerのデメリット
激務になりやすい
入札競争・コスト削減・納期短縮などの影響で、
繁忙期は残業が増えやすい傾向があります。
特に大規模SIerでは、
プロジェクト炎上時の負荷が大きくなりがちです。
また、未経験者や経験が浅いエンジニアの場合
SIerへの入社ハードルが高い点もあります。
SESとSIer、どっちがいい?【キャリア別の考え方】
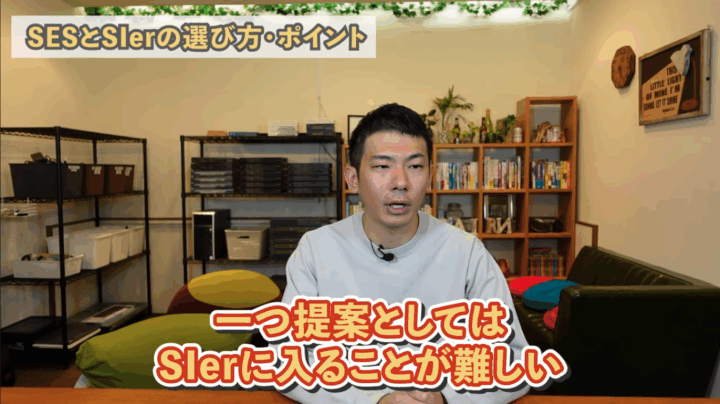
結論として、どちらが良いかはキャリア次第です。
SESが向いている人
-
未経験〜経験浅めで現場経験を積みたい
-
技術を幅広く触りたい
-
将来の方向性を模索中
SIerが向いている人
-
上流工程・マネジメントに興味がある
-
システム全体を設計したい
-
将来PMやコンサルを目指したい
未経験者の場合、
理想は SIerで基礎と上流を学ぶ → キャリアアップ ですが、
採用難易度や働き方の厳しさを考えると、
SESで経験を積んでからSIerへ転職するルートも非常に現実的です。
まとめ|SESとSIerは「優劣」ではなく「役割の違い」
-
SES:現場経験を積みやすいが、給与と上流工程が課題
-
SIer:上流から携われるが、激務になりやすい
-
どちらが良いかはキャリアフェーズ次第
-
自分の将来像から逆算して選ぶことが重要
「SESはやめとけ」「SIerは地獄」といった極端な意見に流されず、
自分にとって何を優先したいのかを基準に判断することが、後悔しないキャリア選択につながります。