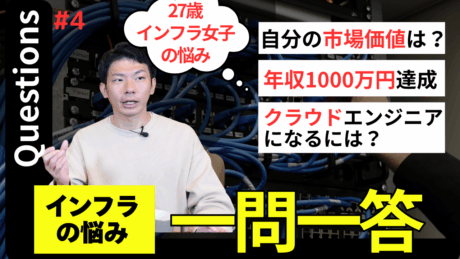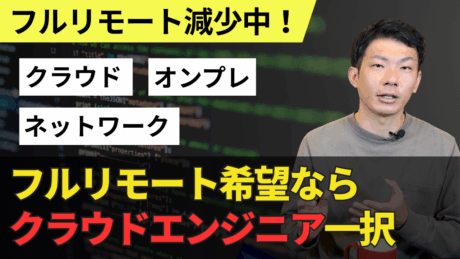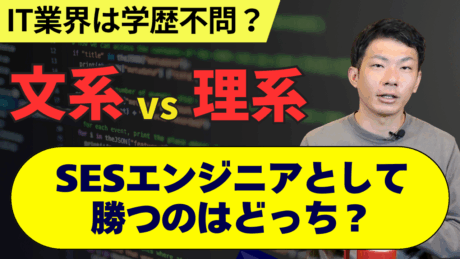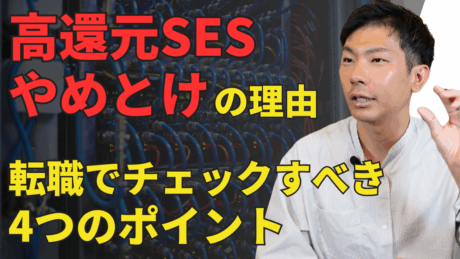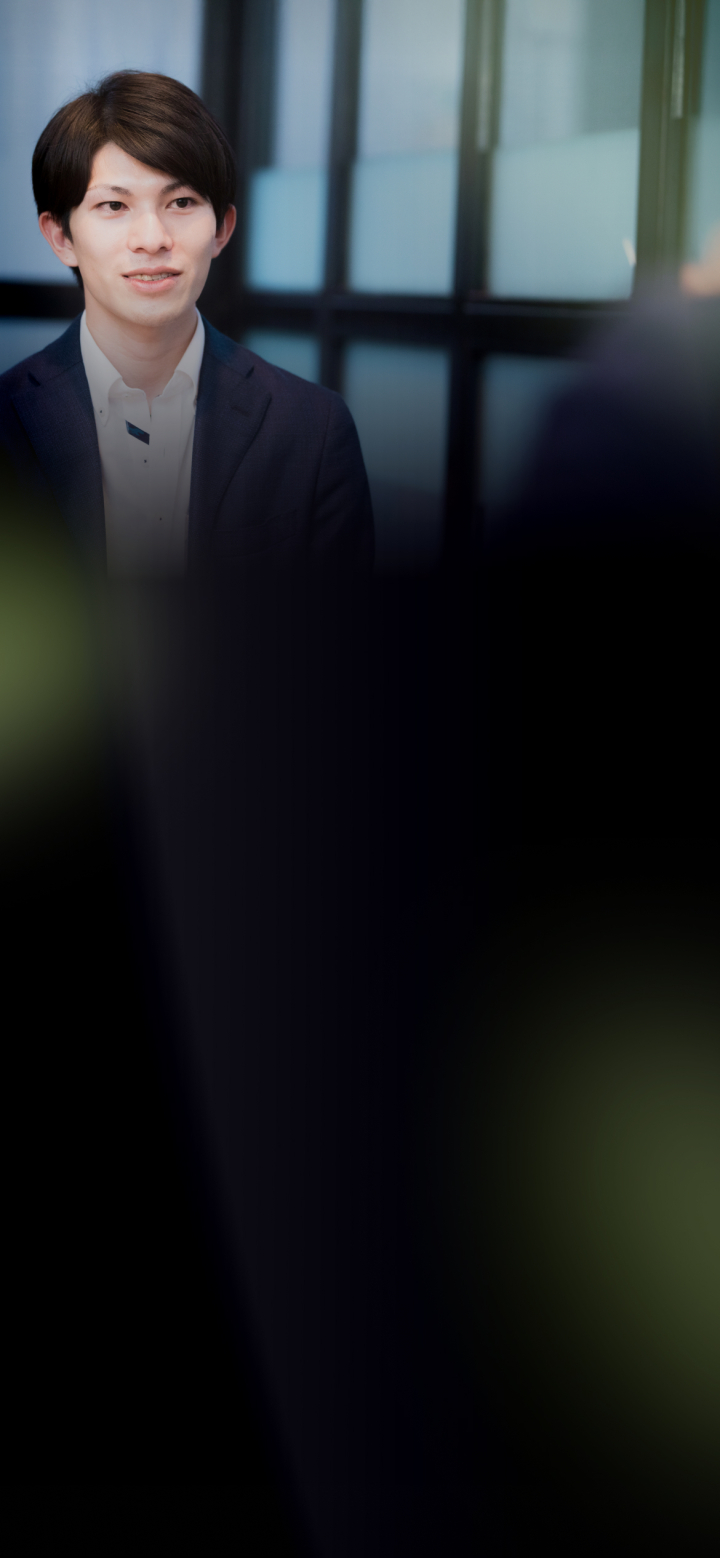投稿日:2025.09.07 最終更新日:2025.09.10
高還元SESと従来型SESの違いを解説

ITエンジニアの働き方としてよく耳にする「SES」。近年は「高還元SES」という言葉も広まりつつあります。では、通常(従来型)のSESと高還元SESは具体的にどう違うのでしょうか。本記事では両者の特徴やメリット・デメリットを整理し、どんな人に向いているのかを解説します。
目次
SESとは何か?
SESとは「システムエンジニアリングサービス」の略で、エンジニアを顧客企業に派遣し、技術力を提供する働き方を指します。自社で勤務するのではなく、顧客先に常駐してプロジェクトに参画するのが基本的なスタイルです。
多くの企業には高度なシステムを自社で構築できるエンジニアがいないため、SIerやSES企業からエンジニアが派遣され、開発や運用を支える仕組みが整えられています。
通常(従来型)のSESの特徴
未経験者を育成する体制
通常(従来型)のSES企業では、未経験者を採用して研修を行い、その後に現場へ配属します。営業担当が用意した案件にアサインされるのが一般的で、自分で案件を選ぶことは難しい場合が多いです。
キャリアの進み方
1つの現場に数年間関わることが多く、2〜3年から、長ければ10年以上同じプロジェクトに在籍する人もいます。その中でリーダーや管理職を任され、社内での昇進を重ねてキャリアを積み上げていくスタイルです。
年収UPは年功序列
通常のSESでは、技術力の向上が直接年収に反映されることは少なく、社内での昇進や勤続年数によって給与が上がる「年功序列型」の傾向が強いです。
メリット
- 未経験からでもスタート可能
- チームでのサポート体制が厚く安心
- 長期的に安定したキャリアパスが描ける
デメリット
- 案件を自分で選べない
- 技術力が直接給与に反映されにくい(年功序列型)
- 長期間同じプロジェクトに縛られる可能性がある
高還元SESの特徴
経験者採用に特化
高還元SESは経験者のみを採用します。未経験者の教育にかかるコストが不要となるため、その分を給与に還元できる仕組みです。
案件選択の自由
自分で参画する案件を選べる点が大きな特徴です。営業主導で案件が決まる通常のSESと比べ、個人の希望やスキルに合わせた案件を選びやすくなっています。
単価連動性
高還元SESでは「単価連動性」が基本となっており、スキルに応じて案件単価が上がり、そのまま給与UPにつながります。さらに、従来型SESに比べて還元率が高いため、エンジニアが得られる報酬も大きくなります。
メリット
- 還元率が高く、給与が単価に比例する
- 案件を自由に選べる
- 技術力を高めれば年収も直結して上がる
デメリット
- 自己管理が必要
- 教育やサポートの体制が薄くなる傾向
- 個人プレーが基本で、チームの安定性には欠ける
通常(従来型)SESと高還元SESはどちらが向いている?
両者は優劣をつけるものではなく、目的やキャリアの段階によって選ぶべき働き方が変わります。
通常(従来型)SESは未経験からでも挑戦でき、組織に守られながらキャリアを積みたい人に向いています。
高還元SESは経験を活かし、自分のスキルを年収に直結させたい人や自由度の高い働き方を求める人に適しています。
ケルンの取り組み:インフラ特化型高還元SES
ケルンでは「インフラエンジニア特化」の高還元SESを展開しています。一般的な高還元SESの弱点を補うため、教育やサポート体制を強化している点が特徴です。
営業体制の効率化
「ケルン=インフラ特化」と認知されることで、案件獲得を効率化。チーム提案も可能に。
実務シミュレーション研修
実際の設計・構築案件をベースに課題化し、若手が現場に近い経験を積める。
実機を使った研修
ネットワーク機器やサーバーを使い、シミュレーションでは得られない実践的な学びを提供。
これにより「高還元SESの給与面での魅力」と「通常SESのサポート体制」の両立を実現しています。
まとめ
- 通常(従来型)SESは未経験から安心してキャリアを積める組織型の働き方
- 高還元SESは経験者向けで、スキルが直接収入に反映される個人型の働き方
- ケルンは「インフラ特化」で両者の強みを組み合わせた環境を実現
エンジニアとしてのキャリアを考える際、どちらの働き方が自分に合っているのかを見極めることが重要です。
👉 「自分はどちらが向いているのか迷っている」という方は、気軽に相談してみるのもおすすめです。